| ホーム > 知ってる? 三重の養殖 |
|
|||||
|
|||
| ■魚類養殖のはじまりは? |
| 魚の養殖は、昭和2年に香川県大川郡引田町の安戸池(海水の池)ではじめられたと言われています。当時は網で仕切った池に魚を入れる方式でしたが、昭和30年頃には、網の生簀(いけす)を、沖合の海に浮かべる「小割式」の方法が考えられました。この方法は現在でも一般的な養殖方法です。 |
| ■三重県では昭和33年頃から |
| 養殖は、昭和33年頃、尾鷲水産試験場が実証試験を行った頃から、三重県下に広がっていきました。 最初はハマチ養殖が中心で、昭和40年代には、生産量が大幅に増え、昭和50年代後半頃にピークを迎えました。 |
| ■タイは全国第4位! |
| ハマチに続き、昭和50年代後半から増えてきたのがマダイの養殖です。これは、稚魚の人工孵化技術が確立されたことなどによるもので、昭和60年代から平成にはいる頃にはハマチの生産量
を上回り、現在では全国第4位の生産量を誇ります。 県内では、ハマチ、マダイのほかにシマアジ、マアジ、ヒラメ、マハタなどが養殖されています。 |
| ■三重県の海では、ここで魚類養殖が行われています |
| 三重県では5市町村にまたがる漁村で魚の養殖が行われています。 |
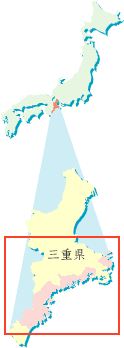 |
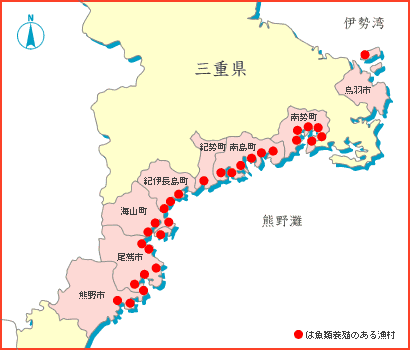 |
|
|||||